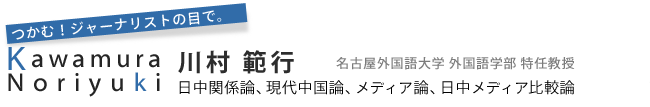第8回日中関係討論会 基調報告「武力ではなく、外交と交流により、東アジアの平和を」
第8回日中関係研究討論会(日中平和友好条約締結45周年記念)基調報告
「武力ではなく、外交と交流により、東アジアの平和を」
日中友好99人委員会会長 川村範行 (名古屋外国語大学名誉教授)
2023年12月9日
尊敬する劉昕生会長(元駐キプロス大使)はじめ外交官OB組織である中国国際友人研究会の皆様、尊敬する御来賓の皆様、ご在席の皆様、おはようございます。日中友好99人委員会を代表して、オンラインではありますが、中国国際友人研究会の皆さんとの再会を心から歓迎申し上げます。本99人委員会と中国国際友人研究会は本年の日中平和友好条約締結45周年の重要な節目に、コロナ禍で中断していた日中関係討論会を開催できることを共に喜びたいと思います。
日中関係は1972年の国交正常化、及び1978年の平和友好条約締結を経て順調に発展してきました。しかし、ここ数年は米中対立の激化とロシアによるウクライナ侵攻により、第二次世界大戦以降の国際秩序が揺らぎ、東アジア・日中関係にも影響が及んでいます。現在の日中関係は、安全保障や経済安保などの諸課題に直面し、国交正常化以来最も複雑で重大な岐路に立っています。
本99人委員会は、日中両国・両国民の間には対話と相互交流による相互理解の促進が必要と考えます。さらに、日中両国は地球温暖化に伴う環境問題やエネルギー問題、貧困・格差問題など共通課題に直面し、世界の平和と安定のために両国の協調は不可欠です。こうした状況下で、今回の討論会では日中双方が日中平和友好条約の意義や日中関係の経緯を回顧しながら、変動する国際情勢のもとで日中関係の新たな在り方について率直な意見交換を通じて、お互いの考えを理解し、以て今後の日中関係の改善と発展に寄与することを強く願います。
私は本99人委員会の会長として今回、基調報告の機会を得て、光栄に存じます。基調報告では次の三点を述べます。第一に、日中関係が国交正常化以来、最も複雑で重大な岐路に立っている現状についてです。第二に、今年8月下旬にコロナ後初の学会訪中団の団長として訪中を実現し、対話交流による相互理解の重要性を強く認識したことです。第三に、日中双方が共に日中関係の原点を確認し、今後の日中関係の発展に努力することです。
1、日中関係の現状
先ず第一の日中関係の現状についてです。
私個人の考えでは、日中関係は1972年の国交正常化以来、四段階で推移してきました。第一段階は、日中国交正常化の実現と1978年の日中平和友好条約締結により、“日中友好の時代”が築かれました。第二段階は、1989年の天安門事件を境に日本人の対中観が変わり、さらに2001年から5年連続して小泉純一郎首相の靖国神社参拝に中国が抗議して、“日中非友好の時代”になりました。そして、第三段階は2010年の尖閣諸島(中国名・釣魚島)海域での中国漁船衝突事件、2012年の同島国有化問題など、領有権問題を巡る“日中対立時代”です。です。第四段階は、安倍晋三首相と習近平国家主席の首脳会談の積み重ねにより、「対立から協調へ」を合言葉に「日中新時代」に向かいました。しかし、米中対立の深刻化やウクライナ戦争の影響を受けて、日中関係は安全保障を巡り複雑な第五の段階に入ったのです。
特に、昨年12月に岸田内閣が安全保障関連文書3件の改訂を閣議決定し、安全保障政策の大転換を図ったことは、日中関係に重大な影響を及ぼします。具体的には敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を認め、防衛予算の倍増を決めたことです。これは第二次世界大戦後の日本の歴代内閣が平和憲法の精神のもとに堅持してきた「専守防衛」の基本方針から逸脱するものです。南西諸島のミサイル防衛基地化を進めれば、中国との間に安全保障上の緊張関係を生じるため、“安全保障のジレンマ”が深刻に懸念されます。
現在の日中関係は三つの課題に直面しています。
(1)「強国」を目指す中国の強硬姿勢に対し、日本政府は日米同盟を基軸に安全保障政策の大転換を図り、中国への対抗姿勢を強めています。“台湾有事”が喧伝される状況下で、日中両国は東アジアの不戦と平和をどう構築していくか。
(2)経済貿易の発展が日中関係を支えてきましたが、厳しい米中対立の情勢下で、米国主導による中国経済切り離しの経済安保政策(デカップリング)が登場し、日中両国はこれにどう対応するか。
(3)コロナ禍で途絶えた日中間の交流を早期に再開し、相互理解を回復することが必要です。中国の国家安全面での管理・規制が厳しくなっている状況下で、日本側が相互交流への懸念を抱いているが、これをどう克服できるか。
2、学会訪中団の交流
第二に、学会訪中団の交流活動からの教訓についてです。私が団長を務める東海日中関係学会の訪中団(6名)が8月27日〜9月1日の6日間、北京及び河南省を訪問しました。ポストコロナ初の日本からの学術交流訪中団として、中国外交部、中国社会科学院日本研究所、中国国際友人研究会などとの交流活動を実現しました。学会設立30周年と日中平和友好条約締結45周年を記念し、日中学術交流を再開し、日中関係の課題とその克服について話し合いました。8月31日に中国国際友人研究会が訪中団のために交流晩餐会を主催してくれたことに対し、改めて感謝します。
訪中団の成果と教訓は3点挙げられます。
①コロナ禍の3年間に日中間の様々な交流が途絶え、安全保障や経済安保などを巡る懸念や誤解などが生じたが、対面による直接交流を通じて相互理解を深め、日中関係改善への率直な協議をすることができた。
②外交部アジア局、日本研究所とも事前の書面質問を受け入れて、丁寧且つ誠意ある回答を用意してくれた。ともに「中日関係を重視」しており、日中関係の改善に日本側の努力を求めている。
③福島原発海洋排水問題が発生し、山口那津男・公明党代表が岸田首相の親書を携えての訪中が取り止めと重なったが、中国側は学会訪中団を予定通り受け入れて、懇談や座談会などの日程も予定通り実施した。今回の訪中団活動は、外交の“第2トラック”の役割に準じる内容だった。
昨年11月に岸田文雄首相と習近平国家主席の日中首脳会談により、対話と交流活動の再開で合意しました。だが、その後の日中関係の動向は必ずしも首脳合意に沿ったものではありません。日中両国政府・政党間の対話を通じた課題解決の努力が必要であり、また民間交流による両国民の相互理解の促進も必要です。
今年11月に同じく岸田首相と習主席の日中首脳会談が実現し、2008年の戦略的互恵関係推進の合意に立ち返りことで一致した。当時日中間で結ばれたプロジェクト43項目を着実に推進する必要がある。
3、日中関係改善への提言
最後に、日中関係の課題克服に向けて、日本側から次の5点を提言したい。
(1)日中両国は今後も、経済貿易を基礎に日中関係を一層発展させるとともに、政府・政党・民間など様々な対話チャンネルによる意思疎通を図り、武力でなく外交力により、ルールを守って東アジアの平和を作りあげていく。特に、安全保障面では両国の防衛関係者の対話と交流を促進し、危機管理メカニズムを活用するなど、信頼醸成を図ることが肝要である。
(2)日本はRCEP、CPTPP、IPEFの広域経済連携(自由貿易)の全てに加盟している立場を活かして、中国のCPTTP加入を受け入れて連携を目指し、中国はCPTPP加入条件を早期に満たすよう努力すべきである。日本はIPEFなどで米国との協調も図りつつ、主体的に多国間貿易を推進する方向で、米中間の調整役を果たし、東アジアにおける安全保障上の緊張緩和に努める。
(3)中国市場において、国際商業ルールに準拠し、透明性のある安定した運用がなされば、日系企業は安心して投資することが出来る。日本企業と中国企業は得意な製品が異なり、「相互補完関係が最も効率的」である。
(4)日本人の訪中(観光など)を促進するために、①日本人の中国訪問時の入国手続きを簡素化する。②日本人向けに魅力ある中国観光企画を工夫し、日本国内の旅行会社に中国観光PRパンフットを増やす。③中国国内で日本人・外国人がクレジットカードで買い物をし易いように工夫する。
(5)中日両国共通の歴史・文化財産として仏教文化を見直し、両国の仏教界が中心となり、“日中仏教フォーラム”を組織し、北東アジアの不戦と平和を訴えていく。中日韓三カ国に存続する“徐福伝説”に関する共同研究や交流を進める。
顧みれば、周恩来総理は日中国交回復の道筋を首脳合意による共同声明と法制化による平和友好条約の二段階で構想しました。日中平和友好条約は国交正常化共同声明に基づいて、重要な3点を明記しています。
1 すべての紛争を平和的手段で解決し、武力また武力による威嚇に訴えない。
2 覇権を求めるべきでなく、覇権を確立しようとする試みに反対する。
3 両国間の経済関係と文化関係の一層の発展、両国民の交流の促進のために努力する。
この3点は、現在の日中関係に於いてこそ、お互いに再認識し、順守すべき事項です。
また、復交前の1962年に高碕達之助氏と廖承志氏の間でLT貿易が締結され、高碕氏は「貿易を妨げるのは良い政治ではなく、貿易は『最良の平和の使者』である」と述べています。高碕氏の言葉の如く、現在のような日中関係が厳しい局面においてこそ、経済貿易の分断ではなく協力こそ必要であります。
私たちはこうした日中関係の原点を見直し、先人の英知に学び、日中関係の課題を克服し発展に努力していくことが大切です。以上を以て私の基調報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。
(付記 2023年12月9日、東京・日中友好会館と北京を結ぶオンライン方式で開催した。日中友好99人委員会は中国外交官OBを中心に組織する中国国際友人研究会と共催で、2002年から日中関係研究討論会を日中両国で交互に開催してきた。日中関係の来し方行く末について、双方が率直な意見交換をし、相互理解を深めてきた。コロナ禍で中断したうえ、2022年9月東京で開催予定が中国側の事情により延期され、ようやく2023年12月に実現した。但し、中国側の原因により訪日代表団を派遣することが出来なくなり、急きょオンライン方式に切り替えた。双方が冒頭挨拶、基調報告とともに、政治外交、経済貿易、メディア・民間交流の3テーマについて事前に発言稿を交換したうえで、当日は真摯な質疑を展開した。双方の考え方の相違点を認識し、さらに一致点を確認することが出来た。オンラインではあったが、対話を通じて貴重な交流を実現した意義は大きい。)